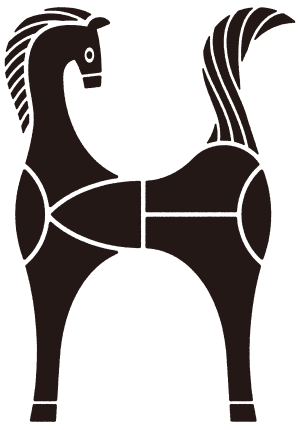第3回目となるカンファレンスイベント「ヒストリカお座敷」。今年も京都文化博物館の6F和室に豪華ゲストをお招きして開催いたします。トークエリア・展示エリアともに入場無料・事前申込不要。誰でもお気軽にご参加いただけます。
入場方法
●トークエリア・展示エリアともに、入場無料・事前申込不要
タイムテーブル
トークエリアの追加セッション、展示エリアのコンテンツも決定次第追加予定!
会場マップ
展示エリア
Cultural Video Production, INVR.SPACE GmbH
『ルイージ・ブローリオの再打ち上げ』は、イタリアの宇宙開発の祖ルイージ・ブローリオの宇宙計画を体験し、その歴史に触れるVR作品です。ヴェネチア国際映画祭の人材育成部門であるビエンナーレ・カレッジ・シネマで制作され、日本初上映となります。今回は3台のVRのヘッドセットマウントディスプレイをご用意しております(無料・プレイ時間は約33分)。※本作品は全て英語での会話となり、日本語字幕表示はございません。プレイ前にスタッフより、物語の解説などプレイのサポートをさせていただきます。
© 2025 つるばみ色のなぎ子たち/クロブルエ
東京国立博物館の共催企画より、新作『つるばみ色のなぎ子たち』の制作資料をピックアップして展示します。※本展示は撮影厳禁となります。
その他に作品の展示や企業の出展なども予定しています。随時更新します!
12月6日(土)
トークエリア1
13:30-14:30
国際映画祭の今、共同制作の秘訣
最新作『LOST LAND/ロストランド』で、第82回(2025年)ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ部門審査員特別賞受賞ほか3冠を獲得し、現在進行形で、平遥国際映画祭(中国)、ボスポラス国際映画祭国際映画祭(トルコ)など世界の映画祭で注目を集め続けている藤元明緒監督を迎え、国際映画祭での反響や様子、また、日本、フランス、マレーシア、ドイツで合作となった経緯や裏側などを、映画コメンテーター・加藤るみさんとともに、深堀りします。
登壇者
藤元 明緒[映画作家]
1988年、大阪府生まれ。ビジュアルアーツ専門学校大阪で映画制作を学ぶ。初長編『僕の帰る場所』(2017)が第30回東京国際映画祭アジアの未来部門作品賞&国際交流基金アジアセンター特別賞を受賞。ベトナム人技能実習生を描く長編第二作『海辺の彼女たち』を公開。同作品はPFF第3回「大島渚賞」、2021年度「新藤兼人賞」金賞などを受賞。ロヒンギャ難民を題材にした最新作『ロストランド』が第82回ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ部門で審査員特別賞を受賞。2026年春全国公開。
加藤 るみ[タレント/映画コメンテーター]
SKE48を卒業後、映画・釣りなど多趣味を生かしマルチに活躍中。『BRUTUS』映画特集、ラジオ大阪で隔週映画紹介、サンテレビ『正月映画大百科』など、関西を拠点に映画コメンテーターとして精力的に活動。
モデレーター
藤井 幹也[フリーライター/Life with movies]
15:00-16:00
2年前の「清少納言は椅子に座れなかったか?」からのはるかな方角への発展
2年前の「清少納言は椅子に座れなかったか?」から始まった探求は、どこに辿り着いたのか?膨大ともいえる監督自身の研究と理解の先に見えたものとは?作品完成を前に、監督自ら語る貴重なトークセッションです。3年連続で語る『つるばみ色のなぎ子たち』制作の舞台裏は必聴です。
登壇者
片渕 須直[アニメーション映画監督]
1960年生まれ。日本大学芸術学部特任教授・上席研究員。大学在学中に『名探偵ホームズ』(84)の脚本を手がける。監督作として、長編『アリーテ姫』(01)、『マイマイ新子と千年の魔法』(09)、『この世界の片隅に』(16)、『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』(19)など。疫病の中に生きる千年前の人々を描く映画『つるばみ色のなぎ子たち』を現在制作中。
16:30-17:30
京都映画賞連携企画
長年にわたり「必殺シリーズ」をはじめとする数々の作品で日本の時代劇映像を支えてきた撮影監督・石原興さん。
登壇者
石原 興[撮影監督]
京都映画株式会社(現・株式会社松竹撮影所)を拠点に、撮影技師のアシスタントとして、数多くの現場に携わる。
昭和47年に、シリーズ第1作『必殺仕掛人』にカメラマンとして参加して以来、陰影を強調した撮影手法で芸術的な「光と影」を生み出し、“必殺”の世界観を築き上げる。
代表作に、『劇場版必殺シリーズ』(撮影監督)、『典子は、今』(撮影監督)、『忠臣蔵外伝 四谷怪談』(撮影監督)、『初雪の恋 ヴァージン・スノー』(撮影監督)、『獄に咲く花』(監督)など多数。平成19年からは、テレビ番組『必殺仕事人』(監督)を現在も撮影中。
平成7年『忠臣蔵外伝 四谷怪談』で、第18回日本アカデミー賞最優秀撮影賞を受賞。京都はもとより、日本の映像産業・文化のレジェンドの一人。
西尾 孔志[映画監督]
1974年大阪生まれ。自主制作映画が評価され、2013年に『ソウル・フラワー・トレイン』で商業映画監督デビュー。続けて2014年『キッチン・ドライブ』、2016年『函館珈琲』、2024年『輝け星くず』を監督する。他に幾つかの映画祭ディレクターや大学講師も務め、関西での映画の人材育成にも力を注ぐ。
トークエリア2
13:00-14:30
短く伝える、広く創るーショートコンテンツ×AIがひらく新時代
映画、CM、SNS、俳句まで——
登壇者
青目 健[株式会社パシフィックボイス プロデューサー]
アパレル企業などを経て現職。横浜・みなとみらいにあったショートフィルム専門の映画館「ブリリア ショートショートシアター」では副支配人を務めた。
主に地域連携事業を担当し、国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」が行う観光映像大賞の遂行、福岡県、長野県阿智村、高知県といった各地域での映画祭・イベントのプロデュースをはじめ、文化庁・日本博事業、愛媛県松山市の文学賞の運営、地域の魅力を発信するショートフィルム制作等に携わる。
亀井 伸幸[立命館大学映像学部 教授]
映像制作会社の制作部・企画演出室勤務を経て、2002年フリーランスとして独立。
CM、PR映画、博展映像、ドラマなど、幅広く映画映像作品の監督、企画演出、脚本を担当。 TVCMを中心に500本を超える作品を手掛ける。ACC他国内外受賞多数有。
日本映画監督協会会員。
立命館大学映像学部では、これまでの豊富な演出経験や広告制作の知識から、映像学部の必修科目「映像制作実習Ⅰ」や、人気授業「広告映像実習」などを担当する。
佐藤 周[映画監督]
1988年生まれ。大分県出身。立命館大学映像学部在学中に制作した短編ホラー『へんたい』が学生残酷映画祭にてグランプリと観客賞をW受賞。その後、心霊ドキュメンタリー『怪談新耳袋Gメン 復活編』で劇場用映画初監督。
2021年には、インターネット社会に飲み込まれた夫婦の承認欲求がもたらす恐怖を描いたPOVホラー『橘アヤコは見られたい』でロッテルダム国際映画祭に正式招待。
2024年には、成人年齢引き下げで18歳から大人となった若者たちの葛藤を描いた『18歳のおとなたち』を監督。
また、プロデューサー兼メイン監督を務めるSNS動画アカウント「コワゾー」はTikTokのホラードラマアカウントとしては国内一のフォロワー数を誇り、TikTok Creator AwardsファイナリストやTikTok TOHO Film Festivalにて観客賞を受賞するなど注目を集めている。
[その他の主な作品]
映画:『ヘタな二人の恋の話』、『シオリノインム』
ドラマ:「怪談新耳袋 暗黒」(BS-TBS)、「ダブルタップミステリー」(テレビ朝日)
おぎゃん
立命館大学卒業。SNS総フォロワー40万人。現在は「はんなりカオスの伝導者」をキャッチフレーズに、舞台とSNSを中心に、役者・インフルエンサーとして活動中
15:00-16:00
ワークショップ:誰が・いつ・どこで・何をした・生成 AI ゲーム
誰でもかんたんに楽しめるAI映像ワークショップを開催します。
16:30-17:30
映画字幕講座①「映画字幕の裏側」:ヒストリカ・ワールド『UBU』
本セッションでは、ヒストリカ・ワールド『UBU』の字幕翻訳者の飯塚純代さんと京都ヒストリカ国際映画祭の字幕制作を担当しているホワイトラインの代表の設楽光明さんをお招きし、字幕づくりの実際を紐解きます。
作品ごとの言葉の選び方、制約の中で生まれる創造性、そして翻訳者たちの“現場の物語”。普段は語られることのない、字幕制作の舞台裏をたっぷりお話しいただきます。
映画ファンはもちろん、字幕翻訳や映像翻訳に興味のある学生・クリエイター志望の方にもおすすめ。
字幕が“もうひとつの演出”であることを、きっと実感できるはずです。
登壇者
飯塚 純代[字幕翻訳家]
字幕講座ONSTA修了後、2024年1月の京都ヒストリカ映画祭「スカーレット」で字幕デビュー。
以降、映画祭を中心に現在まで約10本の作品を担当。
設楽 光明[ホワイトライン 代表]
1980年に字幕制作業界入り。映写技師集団であるスタンス・カンパニーを経て、ホワイトラインを設立。字幕制作を基本とし映像編集、劇場上映素材を制作。自社開発したサブタイトル投影システムは国内外の映画祭で活用され、自身もオペレーターとして参加。山形国際ドキュメンタリー映画祭、なら国際映画祭で上映される、その多くの字幕制作を担当。また1992年には東京国際レズビアン & ゲイ映画祭、参加スタッフに字幕制作ワークショップを自社内で開設。
12月7日(日)
トークエリア1
13:00-18:00
ヒストリカX
詳しくはこちら
トークエリア2
14:00-15:00
グローバルな映画ファイナンス・スキーム実現に向けて
世界では映画が文化事業であると同時に、確立した金融ビジネスでもあります。製作資金はファンドやローンによって支えられ、投資家がリターンを得る仕組みが整備されています。日本ではまだ十分に根づいていないこの 「フィルムファイナンス」 を、京都から実装する第一歩として本セミナーを開催します。これによって日本映画の資金インフラを整え、製作規模の一新を図り、世界に向けて出るためのジャンプ台にしたいと考えます。行政・金融機関・制作現場が交差するこの機会を通じ、映画産業を新たな地域経済の資産クラスとして再定義します。
登壇者
楠 純子[Film Solutions 代表取締役]
銀行勤務の後、国際共同製作におけるビジネス実務を担当、海外の多様な映像ファイナンススキームに触れ、2004年より世界最大手の映画完成保証会社であるFilm Finances Incの日本代表を務める。その後、日活(株)を経て、2020年よりFilm Solutions㈱代表取締役。グローバル基準の製作経理や製作リスク管理など、日本の映像製作ビジネスにおける資金調達の多様化およびグローバル化に不可欠なインフラ整備に注力している。
Film Solutions株式会社:
https://film-solutions.jp/
15:30-16:30
映画字幕講座②「映画字幕の裏側」:ヒストリカ・ワールド『海を約束してくれた先生』
本セッションでは、ヒストリカ・ワールド『海を約束してくれた先生』の字幕翻訳者の安井真琴さんと京都ヒストリカ国際映画祭の字幕制作を担当しているホワイトラインの代表の設楽光明さんをお招きし、字幕づくりの実際を紐解きます。
登壇者
安井 真琴[日英翻訳者、字幕翻訳者]
カナダ留学時代に専門学校で通・翻訳の基礎を学び、帰国後、京都の企業や大学関連機関などで勤務をしながら、社内文書などの翻訳及び通訳を担当。字幕翻訳は、京都ヒストリカ国際映画祭企画の字幕翻訳トライアルをきっかけに勉強を始め、第13回の同映画祭で上映された『モスキート』で字幕デビュー。
設楽 光明[ホワイトライン 代表]
1980年に字幕制作業界入り。映写技師集団であるスタンス・カンパニーを経て、ホワイトラインを設立。字幕制作を基本とし映像編集、劇場上映素材を制作。自社開発したサブタイトル投影システムは国内外の映画祭で活用され、自身もオペレーターとして参加。山形国際ドキュメンタリー映画祭、なら国際映画祭で上映される、その多くの字幕制作を担当。また1992年には東京国際レズビアン & ゲイ映画祭、参加スタッフに字幕制作ワークショップを自社内で開設。
17:00-18:00
京都国際学生映画祭コラボ企画 山口淳太監督スペシャルトーク
本企画では、京都を拠点に活躍する映画監督・山口淳太監督をお迎えし、京都国際学生映画祭の学生実行委員と一緒にトークセッションを行います。学生時代に取り組まれていた自主映画制作のお話から、現在の活動にまつわるエピソードまで、映画づくりの原点を中心に幅広く伺っていきます。
映画制作に日々向き合っている学生実行委員が、プロとして第一線で活躍されている監督にお話を伺うことで、映画監督を目指す学生にとっての学びや新しい刺激につながる時間になればと考えています。また、商業作品とはまた違った魅力を持つ自主制作映画に興味を持つきっかけにもなれば幸いです。
登壇者
山口 淳太[映画監督]
1987年生まれ、大阪府出身。2005年に京都の劇団、ヨーロッパ企画に映像ディレクターとして参加。2020年、初監督した映画『ドロステのはてで僕ら』が多数の海外映画祭で各賞を受賞し、多くの国で配給された。2023年、映画『リバー、流れないでよ』が第15回TAMA映画賞特別賞を受賞。その他の監督作に、クリープハイプ、サバシスター、凛として時雨のミュージックビデオや、連続ドラマ「時をかけるな、恋人たち」などがある。
大島 華[京都芸術大学 映画学科 映画製作コース 2回生/第28回京都国際学生映画祭実行委員]
金 優地[大阪芸術大学 映像学科 2回生/第28回京都国際学生映画祭実行委員]