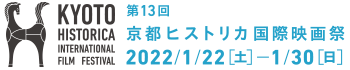お知らせ
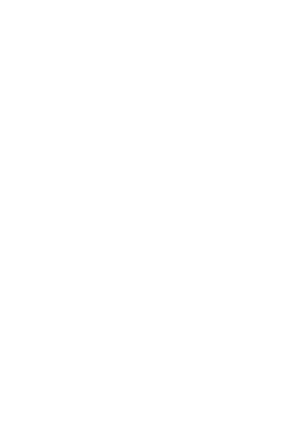
2020/11/7
ヒストリカ・ワールド『モスキート』スペシャルインタビューを公開!
ヒストリカ・ワールド『モスキート』スペシャルインタビュー(2020年10月20日収録)
ジョアン・ヌノ・ピント(監督)(聞き手:京都ヒストリカ国際映画祭 ヒストリカ・ワールド プログラミングチーム)
監督とプロデューサーとの事前インタビューの内容を公開いたします。作品への理解をより深める一助となれば幸いです。
※以下の記事にはネタバレが含まれていますので、ご注意ください。
『モスキート』をまだご覧いただいていない方は、2020年11月8日(日)まで動画配信サイトMIRAIL(ミレール)にてオンライン上映分を販売しておりますので、ぜひお先にご覧ください。→『モスキート(MIRAIL)』 『ヒストリカ・ワールド4本パック(MIRAIL)』
ご購入後は30日間のレンタル期間(初回再生からは14日)がございますので、お好きなお時間にお楽しみいただければと存じます。

ジョアン・ヌノ・ピント(以下、ジョアン):
今年の初め、ポルトガルで公開される1週間に前に映画館がロックダウンされてしまいました。制作に7年もの歳月を費やして、素晴らしい作品を作ったのに全部むちゃくちゃになってしまったんです。ワールド・プレミアの1週間後にこんなことになってしまい……。でも私だけじゃなくて、みんな台無しになっちゃったんです。でも映画祭をやれてよかったですし、今回、日本で上映していただけること大変感謝しております。
●制作に7年を要したという本作品ですが、この企画の成り立ちは?
ジョアン:
実は、私が一番最初の劇映画を作る前から『モスキート』のアイデアがありました。ただ、すごく複雑な企画だったので、最初の映画として作るには適していないと思い、寝かせていたんです。
まずは妻と一緒に脚本を書き始めました。予算の工面や脚本の準備に最初の3年を費やしました。脚本が全部完成する前にモザンビークに渡り、5000kmくらい旅をしました。本物のアフリカを知るために、旅をし続け、色々なものを自分の目で見ました。映画でもよくあるヨーロッパ的な視点ではなく、100年前のアフリカは実際にどのようだったかというのをちゃんと見たかったので、リサーチにはかなり時間がかかりました。
やっと準備が整って、もう一度モザンビークに行こうという時に、モザンビークで政府と反政府の人びとの間に紛争があり、危険な状況のため、先延ばしにしないといけなくなりました。しかも、元々はモザンビーク北部での撮影予定でしたが、北部が危険ということで中心部より以南での撮影に変更となりました。北は森林が多く、南はサバンナという感じで、風景が全く違う。物理的な風景は内情を見せるものであるから、それをちゃんと表現できるように脚本を書き直さなければいけなくなったのです。リスタートするために2年くらいかけて脚本を書き直しました。
●そういった綿密な準備がしっかり絵に出ているように思います。
ジョアン:
悪いことがあっても、その中には良いことも見つけられます。今回の場合は、たとえ残念なことがあっても、それをどう活かすかということを考えるきっかけになったので、その点では良かったと思っています。何度も何度も先送りになり、調整をし直し、銃だったり色々な小道具も必要だし、限られた予算で、時代劇で、しかもアフリカで……いかに達成するかという解決策を見つけなければいけませんでした。先住民の村も一から作りました。
●撮影日数としてはどれくらいですか?
ジョアン:
約2ヶ月です。5週間はモザンビーク、3週間はポルトガル。ポルトガルでは、ヨーロッパ人が多い船のシーンやキャンプ、野戦病院のシーンを撮影しました。
●プロダクション自体の人数はどれくらいですか?
ジョアン:
クルー自体はかなり少人数です。各部署のトップはポルトガルから一緒に行きましたが、現地の人に手伝ってもらうことが多かったです。メイクの担当者はザカリアスの変貌から、他の登場人物や特殊メイクにいたるまで、たった一人ですべてを成し遂げてくれました。
映画自体が物理的にずっと移動し続けるロードムービーなので、途中でストップしたり、食事したり、泊まったり、かなり過酷な状況でした。そういう状況で撮影をするためにはクルーが少ない方が管理しやすいという理由もあり、クルーは最小限でした。その中でもトラブルも多くて、先住民の村をセットする時も最初に許可を取っていたはずなのに、別の人物が出てきて、ここではダメだと言われて、また場所を探すところから始めなきゃいけなかったり……。
ただ最初からこの映画は厳しい環境で作らないといけないというのはわかっていたんです。その厳しい環境下で撮影すること自体が映画の登場人物だけでなく、クルー全体の空気として、映画の言語に変換される。これが重要なのです。それを体験したスタッフの気持ちや感情がないとああいう映画は作れなかった。
●撮影を通して、プロダクション自体が変貌していく、私たちは観客としてザカリアスの踵を追って旅をする。私たちもザカリアスも変わっていくし、きっと撮影した監督やスタッフも変わっていったんだろうと感じました。そういう変身していく物語として、フランシス・フォード・コッポラ監督の『地獄の黙示録』(1979)がリファランスとしてあるかと想像しているのですが、いかがでしょうか?

ジョアン・ヌノ・ピント監督
ジョアン:
たしかにリファランスとして『地獄の黙示録』の存在自体はあるのですが、明確に参照したというよりも、自分自身が小さい頃に観たという体験が自分の背景にあるという感じでしょうか。登場人物や撮影現場の狂気みたいなものが絵に映し出されるという意味ではヴェルナー・ヘルツォーク監督の『アギーレ/神の怒り』(1972)もそうです。
それらの作品とは少し違うことがしたかったし、ヨーロッパ的な視線で新世界的にアフリカを見ているという感じで、人種差別的な視点があり、アフリカは危険と断定的です。アフリカにある資源や魅力的なものに惹かれていったはいいけど、わからない、未知のものであるアフリカに冒されておかしくなっていくみたいな視点が多いのですが、『モスキート』では、最初は観客はザカリアスとともにあり、彼が理解できることは理解でき、理解できないことは理解できない、というように同じ感覚を共有している。しかし、先住民の村に行った時点で、それが完全に逆転してしまい、完全に村の立場の目線になってしまう。ここで、急にザカリアスはよそ者になるし、何も理解できないということを理解させられるというのを観客として共有できる。実際に中に入ってしまったら、先住民である彼女たちは危険な存在ではなく、彼女たちは彼女たちの社会だったりルールを持ち、自分たちは自分たちで安全に生活している、と。この環境に入ってしまうと、野蛮なのは軍人である西洋人のほうなんです。そういう視点を見せたかったというのはこの映画の一番のポイントです。
●たしかに、先住民の女たちしかいない村にたどり着き、首に鎖をつながれ、奴隷化していくザカリアスという図は他の映画ではあまり見たことがありません。この映画に一貫している人種や文明の上下みたいなものに対して、非常にわかりやすいイメージになったと思います。『地獄の黙示録』も『アギーレ/神の怒り』も、主人公は成人した男性ですが、ザカリアスはまだ若い。変貌する余地があり、ドイツ兵に対して威張っていても、祖国を代表して威張っているという大層なものではなく、強がりを言っているだけのような軽さがあって、その彼と一緒に旅をしている私たちもそういう気持ちにシンクロしているわけですが、私個人としては、湖に出たシーンで圧倒的に解放される感覚があって、ザカリアスとしての私はあそこでハッピーに物語を締めくくりたかったという気持ちもあります(笑)。確かに最後のくだりをいれないと、ストーリーとしては成立しないんだろうなというのはよくわかるんですが、詩的で陽気なロードムービーとしての『モスキート』で僕が愛するのはあの湖のシーンです。
ジョアン:
ザカリアスは最初から最後までずっと愚かな選択肢を取り続けているという象徴なんですよね。ヒーローというより、悪役みたいなことをやり続けています。監督の私にとって難しかったのは、ザカリアスは常に間違った選択を取り続けてもらわないと困るのですが、それでも観客の共感を忘れてはいけないから、そのせめぎ合いに結構悩まされるところが多かったんです。でも、ザカリアスは悪い選択肢ばかりを選んでいくのですが、同時にその選択肢を選ばないという選択肢は何度も与えられているんです。最初にキャンプを見つけた時も、先住民の村に着いた時も、ドイツ兵に出会った時も……。別に反抗せずとも、別の選択肢を選ぶ機会は何度もあるにも関わらず、そのまま突き進んで、どうしても愚かな考えを選んでしまう。結局、最終目的地に辿り着いて、ザカリアスは何を学んだのかというと、彼は実際には戦争には行ってなくて、彼の中の戦争(=コンラッド『闇の奥』)は想像していた頭の中の戦いだけで、そんなに勇敢なものでも誇り高いものでもなく、ずっと求めていた戦いもドイツ兵と出会ったときに、やっと成し遂げられると思ったのに、ドイツ兵も結局ただの一人の人間だった。その結果、彼はドイツ兵は敵でもなんでもなくて、戦争も思い描いてた美しいものでも誇らしいものでもなんでもないということを学んでしまった。彼のコンラッドは存在しなかった。一番最後のライオンのシーンは、ギリシアの古典でもあるように、自分の親のような存在である分身を殺さないと自分は一人の男になれないという象徴としてあのシーンを入れなければいけなかったのです。
●洞窟の中で、懺悔・告解している時に出てくるひょうたんを持った男性はどういう存在で、何を示しているのでしょう?
ジョアン:
『モスキート』では、モザンビークで起こっていることが現実世界でのコロナイゼーション、ひょうたんを持った男性の存在は精神世界のコロナイゼーションを表現しています。あの場面では、ザカリアスはすでに病に参っており、諦めて告解しています。ザカリアスがそのまま諦めてしまったら、こうなるというのを見せるために、メッセンジャーというか、そういう役割で彼がいます。でも、この時すでにザカリアスは正気ではないので、本当に彼が実在しているのか、ただの妄想なのかはわかりません。ただそれはわからないままでいいんです。好きなように解釈していただければいいです。ただその象徴としては、ザカリアスが諦めてしまって、そのまま病に負けるとこういう風になるよっていうのを体現する存在となっています。
あの場面は編集の仕方も他の部分とは違います。基本的にロングショットで撮っていますが、あそこはバシバシとカットしているし、繋がりもぐちゃぐちゃに感じるだろうし、目の前に立っていたはずなのに、急に後ろに行ったりとか、わざとそういう演出にしています。ザカリアスと同じ精神状態で、何が起こっているのかわからないんです。
●プロダクションと同時にいろんな人が変貌していったと思うのですが、特にザカリアスの俳優に対して、アドバイスというか、どういう演出をしながらあの撮影をしていったのかが気になります。彼の演技は圧倒的でした。
ジョアン:
確かにこの2年間は色々な話し合いをしましたが、彼は役者としての頭が非常に良く、このキャラクターを完全に理解しており、基本的には彼の中にすでにザカリアスがいた、というか、もともとあったものという感覚でしょうか。なので、特に演出はしてないんですよね。ただ、その中でも何かひとつ重要だということがあるとすれば、当時の少年の考えを大事にするということ。ザカリアスの誇りみたいなもの、彼の場合は歪んだ自分像です。実際よりも自分を大きく強く見せているという愚かさのような誇り。本当の現実とは違うけど、自分は今の状況よりももっといいものを与えられるべきっていう考えがある。そういう自分像みたいなものを重要視していました。
ザカリアスの俳優はすごく責任重大です。映画を通して、彼が存在しない空間というのはほぼない。すべてがザカリアスの肩に乗っていて、常にザカリアスが中心にいる。あの役者を見つけた時は本当に心からホッとしましたよ。
●どうやって彼をキャスティングしたんですか?
ジョアン:
基本的に役者はキャステイング担当がオーディションをおこないました。オーディションのやり方も、軍隊のスカウトみたいな感じで、みんな揃ったら大声で怒鳴り始めて「服を脱いで横になれ!」みたいな感じで従わせるようなものでした。設定が過酷というのもありますが、撮影現場はかなり過酷なものになるというは確実だし、レジリエンスの高い人じゃないと出来ないと思っていたので、それを見抜くためにそういう形をとりました。実際に軍隊の入隊試験だったりとかって、その人のキャラクターがすぐに見抜けるし、精神的に弱い人はすぐに折れちゃうっていうのも目に見えてわかります。ザカリアスの役者であるジョアン・ヌニェス・モンテイロは、みんなの中で身体が一番小さいし、弱そうに見える。しかし、一目見ただけで、彼の心の中のジャイアントが見えるというくらい目立っていて、すぐに彼がいいというのがわかったんです。なので、彼がザカリアスが決まった時に、彼に合うように脚本を調整し直しました。彼のように、「蚊(モスキート)」は見た目は弱そうに見えるけど、条件が揃った時にすごく凶暴なものに変化する。そして、タイトルは役者が決まってから『モスキート』となったんですよ。
●ジョアンさん、貴重なお話をどうもありがとうございました!