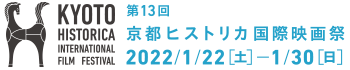お知らせ
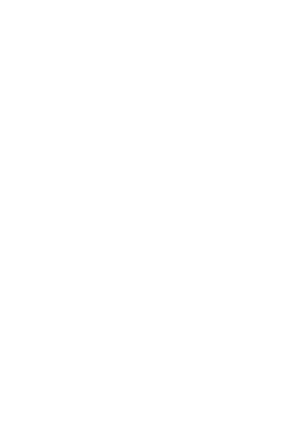
2020/11/5
ヒストリカ・ワールド『義理の姉妹』スペシャルインタビューを公開!
ヒストリカ・ワールド『義理の姉妹』スペシャルインタビュー(2020年10月20日収録)
クリスティーナ・シボラップ(監督)、ナディア・ザイオンチコーヴスカ(プロデューサー)
(聞き手:京都ヒストリカ国際映画祭 ヒストリカ・ワールド プログラミングチーム)
監督とプロデューサーとの事前インタビューの内容を公開いたします。作品への理解をより深める一助となれば幸いです。
※以下の記事にはネタバレが含まれていますので、ご注意ください。
『義理の姉妹』をまだご覧いただいていない方は、2020年11月8日(日)まで動画配信サイトMIRAIL(ミレール)にてオンライン上映分を販売しておりますので、ぜひお先にご覧ください。→『義理の姉妹(MIRAIL)』 『ヒストリカ・ワールド4本パック(MIRAIL)』
ご購入後は30日間のレンタル期間(初回再生からは14日)がございますので、お好きなお時間にお楽しみいただければと存じます。

クリスティーナ・シボラップ(以下、クリスティーナ):日本で上映されるのがすごく嬉しいです!来週の金曜日(※インタビュー時)にポーランドのワルシャワでの上映が決まっているのですが、大きなスクリーンで上映できることがとても嬉しいんです。2020年1月に公開されたので、スクリーンで上映できるのはすっかり珍しいことになってしまいました。この映画は大きいスクリーンで観るのと、オンラインなどで画面上で観るのと、全然違うんですよ。ぜひ楽しんでほしいです。
●この映画はウクライナ国内に向けて、もしくは世界に向けて、どちらを想定して製作を始めたんでしょうか?
ナディア・ザイオンチコーヴスカ(以下、ナディア):舞台はウクライナとポーランドですが、当初からインターナショナルでのセールスを想定していました。ウクライナという場所は、ロシアやポーランドをはじめ、いろんな国との境目に位置しています。本作品で描かれている1900年はオーストリア・ハンガリー帝国の東部に位置していましたが、ウクライナ対ポーランド、対ソビエトなど、戦争で国の所属が変わってきた歴史を持っています。なので、文化的な交差点というような感じでしょうか。実際に当時のウクライナには9種類くらいの国籍を持つ人びとが住んでいたようです。話される言語も、ドイツ語、ポーランド語、ウクライナ語を中心に複数あり、それらの全部の言語を話すことはできなくても、みんな2つくらいはだいたい話せたようで、話せなくても、理解できる言語はいくつかあったようです。ウクライナにはこういった背景があるので、舞台である国はウクライナですが、国際的に配給することを想定して作っていました。
クリスティーナ:日本のみなさんがどんな反応をするのかまったく想像つかないんですが、日本でこの映画が受けるのかすごく気になります。
●原作であるベストセラー小説、ソフィア・アンドルホビッチ著『フェリックス・オーストリア』について教えてください。
ナディア:一番最初に、ウクライナとポーランドで出版されて、そのあとは7ヶ国語に翻訳されています。主人公の二人はポーランド人とウクライナ人という設定なんです。その時代の背景からすると、ウクライナ人の方が貧困層でした。今回の映画はポーランドとの合作を予定していましたが、色々な経緯があり、ウクライナだけで制作することとなりました。ステファ役のマリアンナ・ヤヌシェビツはポーランド人ですけどね。原作小説は、現代に書かれた小説では、ウクライナで一番売れたのではないでしょうか。古典以外の内容でこれだけ売れたのは初めてだと思います。なので、予算をかけてちゃんと素晴らしい作品を作りたかったんです。予算は日本円で約2.4億円で、ウクライナの映画としては相当大きな金額です。こういった強い思いがあるので、わたしたちの文化に対しての理解がある中央ヨーロッパや東ヨーロッパだけでなく、日本でも上映していただけるということをとても嬉しく思っています。
●映画にあるサーカスのシーンですが、カツラをかぶり、着物のようなものを着た東洋人っぽい登場人物も出てきますが、この登場人物の存在の意図みたいなものはありますか?
クリスティーナ:
当時のヨーロッパでは、おそらく割とどこでもそうだったかと思うのですが、東洋人はエキゾチックな存在としてみられていたので、ファンタジックなものを表現するのによく使われています。文化的な背景に加えて、純粋に見た目、視覚面でも美しいですし。この映画は、衣装にもすごくこだわりがあるので、赤色を基調に、かなり色々なものを探しました。
ナディア:
演じているのは、エカテリーナ・クハルというウクライナの国立オペラに所属するバレリーナです。彼女はベリーダンサーでもあるので、動きにくい大きなカツラでもうまく演じてくれました。高いところから落ちるシーンがあり、当初はスタントを入れる予定でしたが、彼女はそれを断り、何度もリハーサルを重ねて、自ら落ちるシーンをやってくれました。彼女はウクライナ国内では知らない人がいないというくらい有名な方です。そのシーンは、400名くらいのエキストラがいたのですが、私たちがプレスで情報を出すまでは、必ず彼女が出演していることを漏らさないようにと同意書にサインをしてもらいましたが、彼女が舞台に出てきた瞬間、みんなスマホを掲げて写真を撮っていましたよ。(笑)
●ステファとアデーラの関係性についての質問ですが、ステファの勘違いというか、観客の私たちもミスリードをしてしまうように描かれていたと思います。

クリスティーナ・シボラップ監督
クリスティーナ:
原作小説だと、最初から最後までステファの視点で描かれています。最後になるまで、彼女の幻覚や妄想というより、ただの勘違いであるいうことは観客にはわかりません。ただ、映画にすると、文字だけではない視覚的な情報が入りますし、物理的に他の人間も入ってきてしまいますよね。脚本の段階でこのあたりはかなり工夫をしなければいけなかったんです。そこで、単純にアデーラが悪役という風には描きたくなかったんです。その駆け引きを、ステファの妄想なのか、それとも真実なのかというのを少しずつ明らかにしていくという手法をとりました。いろんな人にそれぞれのストーリーがあるので、それを表現できるようにしたかったんです。
●女の子が主役で、ルックも華やかでオシャレでこだわり満載で、ガールズフィルム的な側面があるのかなとも思ったのですが、そういった映画や人物など参考にしているものはありますか?
クリスティーナ:
他の映画が要因というわけではなく、原作小説にすべてが詰まっていました。この本では、ステファは1900年代のウクライナの女性の標本みたいな象徴として描かれているんです。彼女はまさに自分を犠牲にしてでも人のために尽くすという人物です。すべての人間に尽くしたいけど、自分のためにはなんにもしない。これは何も100年前のウクライナにとどまらず、今を生きるウクライナ人の女性も、ステファみたいに自分を犠牲にして、他人に尽くすという動機で行動する人が多いんです。ただ、私はこの考えを全然理解できないんです。なぜなのかわからないんです。でも、100年前でも今でもステファみたいな人が多いというのは事実です。わからないからこそ、この問題を考えるきっかけとしてこの映画を作りました。
ナディア:
ウクライナの国の背景として、常に何かに抑圧されてきている立場っていうのをずっと持っているんですよね。ソビエトから独立したのも1991年と最近です。今では公用語はウクライナ語ですが、以前は第二言語として扱われてきたという状況もあります。そして、原作小説は、ほとんどウクライナ語で書かれていてますが、当時の歴史背景や使われている言語の混じり具合、人びとの生活から方言にいたるまで、とても正確に表現されていました。今の若い世代は、昔のウクライナのことを全然知らないんです。本当に何も知らないと思う。この小説を読んで初めて、昔のウクライナを知るんです。私はポーランド人のクォーターなのですが、色々な要素のあるこの小説に共感できる人が多いと思うんです。普段から本を読んでいますというような読書好きではなくても、一般的な層の方が初めてウクライナの本を自発的に読んだのはこの小説が初めてだと思います。やっとこんな小説が出てきてくれたんだと非常に感銘を受けたんです。
原作者のソフィアのお父さんもウクライナではかなり有名な小説家です。そういう環境だったので、彼女はすごくプレッシャーを感じることもあったでしょう。彼女もやはりこの街の出身で、時代考証などのリサーチはもちろんですが、それよりも肌感覚として街のDNAを持っているんです。それがこの小説の大きな説得力となっています。
原作者も含めて、この映画がいろんな人のデビュー作にもなっています。クリスティーナも初の長編監督でしたし、コスチュームデザイナー、作曲家、そして私自身もプロデューサーとしては活動していましたが、最初から最後まですべて関わるのは初めてでした。主演のステファ役の女優もポーランドで子役でテレビに出てたのですが、しばらく女優業から遠のいていたので、復帰作となりました。
●自分たちのアイデンティティを託せるものが出てきたというのがガールズフィルム的なビジュアルなのはとても面白いと思います。そこで、映画のビジュアルのですが『アメリ』や『チャーリーとチョコレート工場』などを彷彿とさせる雰囲気もありました。魚が喋ったりもしますよね。
クリスティーナ:
この映画はすべてステファの視点で描かれています。実は、魚が飛んだり、喋ったりというような描写は原作にはないんです。なぜこれらが登場したのか?それは、文字では決して表現できない、私たちの観ている世界はステファの心の中の世界であることを絵で見せないといけないからです。観客が観ているものはステファの視点だということを表現しないといけません。ステファはすごく孤独な子です。自分の表現の中で生きている。脚本部分のファンタジーの表現に加えて、撮影での工夫として、いろいろと相談して、日常の中でステファが大切にしているもの、彼女にとって大事なものを表現するために、料理のシーンや食べ物を特殊なレンズを使って撮影しました。マジシャンの男性などは原作には登場せず、脚本段階で足した要素です。

ナディア・ザイオンチコーヴスカ プロデューサー
ナディア:
装飾や美術周りの部分は、この映画で一番予算がかかりました。ウクライナは、ポーランドだったりソビエトだったりと、国の所属が変わり続けているというお話を先ほどしましたが、これによって、建築物や街並みなどの外観も変わり続けているので、該当する場所がなくて、撮影できなかったんです。
実際の現場の家はまだ実在するのですが、外装はそのままでも、内装が変えられていたり、所有者もバラバラなので、そこでの撮影が現実的ではなかったのです。なので、キエフの郊外で街自体を再現して作りました。外のシーンは街で撮影して、内装はセットを作って対応しました。
CGIやVFXを担当してくれた方はかなり頑張ってくれたので、最終的には共同プロデューサーとしての地位を与えました。YouTubeにも彼らの頑張りがわかる動画がたくさんあるので、よろしければみなさんも是非観てみてくださいね。
●本作品で出てくるお料理のシーンは本当に印象的で、ステファの用意した食卓は本当にたくさんの美味しそうな料理で溢れかえっていました。映画において重要な役割を担っていたように感じます。
クリスティーナ:
食事やお料理のシーンは、ステファの精神世界を表現するためにファンタジーっぽく見せてはいますが、実際当時文化が強くあらわれる重要なものです。例えば、地位のある家庭は社交の一部として料理を振る舞い、自分たちのステータスを見せるために食べ物が使われていました。当時は食べ物は保存がきかないので、毎日、毎食、最初から作っていました。ステファも毎日何時間もの時間を料理に費やしていました。実際に自分たちのおばあちゃんの世代はその名残がありますね。
ナディア:
実は映画の制作段階でマーケティングの一環として、古いレシピを集めるブロガーの方と料理本を作る企画をし、実際に出版されています。こちらもYouTubeに、実際のお料理動画もたくさんアップされているので、FILM UAグループのチャンネルを是非ご覧くださいね!
●クリスティーナさん、ナディアさん、貴重なお話をどうもありがとうございました!